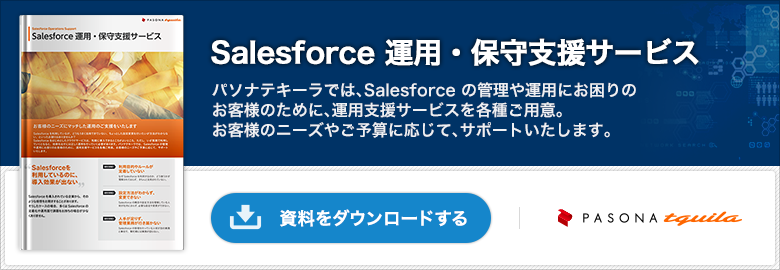CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント:顧客関係管理)を導入することは、徹底した顧客情報管理とその共有環境、およびマーケティング実施による見込み客創出や既存顧客の維持といった、現代ビジネスに不可欠な環境を手にすることです。もちろん、これらは企業要件に沿った正しいCRM導入ができた場合に限ります。
CRM市場は現在、年々拡大傾向にあり顧客情報管理をもとにしたOne to Oneマーケティングが、いかに多くの企業に求められているか、うかがい知ることができます。しかし、必ずしもCRMを導入すれば、確実に導入効果を得られるわけではありません。
CRMの導入にはいくつかの落とし穴が存在し、その第一関門である製品選びでつまずく企業も多く、適切な製品選定ができないことでシステムが定着しないなどの問題が起きています。そこで本稿では、今後CRMを導入しようという企業に向けて、正しいCRMの選び方をご紹介します。
選び方1.CRMの役割を改めて理解する
選品選定の具体的なポイントに入る前に、CRMの役割をここで整理しておきます。その理由は、CRMというシステムについて曖昧に理解してしまっている場合が多く、ゆえに正しい製品選定ができないためです。
CRMは、営業活動を効率良く行うためのSFA(セールス・フォース・オートメーション:営業支援)と違い、顧客情報を集約管理することで、営業やマーケティングへの活用や顧客への細やかなサービスおよびケアの展開を実現するためのシステムです。
従来の顧客データベースのように顧客の基本情報だけで止まらず、顧客企業の担当者や決裁者、取引履歴、活動履歴などのあらゆる情報まで管理し、それをシステム上に集約します。こうした顧客情報は今まで営業担当者ごとに属人化していることが多いため、組織として顧客に接することができないという欠点がありました。CRMに顧客起点のあらゆる情報を集約することで、営業部内だけでなくサポート部門、マーケティング部門なども適切な業務を実践することが可能になります。また、経営者や営業責任者はデータ分析とマーケティングへの活用を可能にします。
こうした特長を持った機能を活用することで、顧客満足度向上に伴う企業収益拡大を図るのがCRMの役割です。そのため、CRMは導入してすぐ効果が表れるものではなく、中長期的な視点で導入効果を想定することも大切です。
選び方2.想定する課題と、現実の課題とのギャップ
顧客管理において経営陣が想定する課題というのは、必ずしも現実の課題とは一致しません。改めて営業担当者や部署責任者にヒアリングしてみると、想定していた課題と現実の課題との間に、大きなギャップがあったりします。
そこで、まずは顧客管理における課題の洗い出しから始めます。経営課題というのは明文化し、実際に顕在させてみないとその全容を把握できない場合ほとんどです。「我が社の課題は○○だ!」と調査もせずに決めつけては、間違った課題認識のままCRM導入が進んでしまい、結果として製品選定はもちろん運用にも失敗してしまいます。失敗するだけならまだしも、CRMは高額な製品なので「導入したからには」と無理にシステムを利用させようとすると、マーケティングや営業効率が下がり業績悪化に陥ります。
そのため、必ず最初に顧客管理の課題把握を実施しましょう。
選び方3.CRM導入は本当に必要なのか
失敗してしまったというより、もったいないケースとして「CRM導入の必要がないのに導入した」という場合もあります。CRM導入には失敗していないものの、そもそもCRMを導入せずとも課題を解決できたり、ちょっとした工夫で業務改善が行えるようなことも少なくないのです。
従って、顧客管理の課題を明確にしたら、すぐにCRM導入に踏み込むのではなく、一度立ち止まって「本当にCRM導入は必要なのか?」と自問してください。たとえシステムが定着しても、不要なものを導入することほどもったいないことはありません。
選び方4.課題解決は具体的な要件に落とし込む
顧客管理に関する課題をすべて把握して、CRM導入の必要性も十分に検討した。次の取るべきアクションは具体的な要件定義です。CRMの製品選定は予め定義した要件に沿って選ぶのが基本であり、要件とは製品選定をする上での基準でもあります。
要件がそもそもない、あるいは要件に沿わない製品選定をしてしまうと、間違ったCRMを導入してしまう可能性があります。
ただし注意していただきたいのは、要件自体がそもそも間違っていると正しいCRM選びはできないということです。では、どうすれば正しい要件定義ができるのでしょうか?
その答えが営業責任者や営業担当者、その他のユーザーを巻き込んだ要件定義を行うことです。
CRMは顧客情報を集約し、マーケティングや既存顧客へのサービス、および顧客分析などに活用するいわば「経営向けの顧客管理システム」です。要件には経営目線での要望が増えてしまいがちですが、システムを利用するのはあくまで現場です。彼らにとってCRMを利用するメリットが無ければ、システムは上手く定着しません。経営者のトップダウンによって無理やり定着させるケースもあるものの、ユーザーのフラストレーションが溜まるのは明白です。
ですので、要件定義は経営視点でのみではなく、確実に現場の声を取り入れたものにしてください。情報システム担当者の独断で要件を定義するのも、もちろん危険です。
選び方5.クラウドか、オンプレミスか
「クラウドファースト」という言葉をご存知でしょうか?これは、新しいシステムの導入や刷新において、クラウドサービスの利用を優先的に考慮するという考えです。「クラウド」という言葉が誕生して十余年、これは単なる言葉ではなく一つのシステム導入選択指として無視できない存在になっています。
CRMにおいてもクラウドサービスで提供されている製品が多数登場しています。CRM/SFAのリーディングカンパニーであるSalesforceにおいても、「Sales Cloud」というクラウドCRMプラットフォームが提供されています。
クラウドでCRMを導入するメリットは、初期導入コストや運用コストの低減と拡張性、柔軟性の高さです。さらに、異なるデバイスからでも同じシステムにアクセスできるので、インターネット接続環境さえあればデバイスや場所を選ばないという機動力の高さも魅力ですし働き方改革という面でも優れた環境と言えるでしょう。
多くのCRM製品はタブレットやスマートフォン向けのクライアントアプリなども備わっているため、CRM活用の範囲が大幅に広がります。
一方オンプレミスでは、導入コストと運用負担がかかるものの、柔軟にカスタマイズ可能であり100%に近い形で要件に沿えるというメリットがあります。
選び方6.ベンダーの生存能力(バイアビリティ)
最後のポイントとしてベンダーの「生存能力(バイアビリティ)」を挙げます。ベンダーの生存能力とは、文字通り将来にわたってCRMを提供するベンダーが企業として存続するかの力です。
変動が激しいIT業界では、吸収合併や倒産によって、CRMを提供するベンダーがその経営形態を変えてしまったり、存続できなくなる可能性が大いにあります。
その際のしわ寄せを受けるのはCRMを導入したユーザー企業です。CRMの機能が大幅に変わったり利用料金が高騰するといったケースも少なくありません。ですので、選定するCRMベンダーの生存能力も十分考慮し、正しい選定を行う必要もあるでしょう。
選び方7.信頼できるパートナーがいるか
CRM製品をいざ導入しようとするとカスタマイズをしたくなったり、運用をお願いしたくなったりとあらゆる課題が浮かび上がってきます。また、自社の要件にあったことが候補のCRM製品にできるのかどうかのPOCなども必要になるかもしれません。そのような場合にはその領域において豊富な知見と経験のある信頼できるパートナーが必要不可欠になります。そのような場合に備えてパートナー選定も行っておきましょう。
皆さんのCRM選びが、少しでも正しく成功するものになれば幸いです。
- カテゴリ:
- その他
RECENT POST「その他」の最新記事
RANKING 人気記事ランキング
RECENT POST 最新記事
TOPIC トピック一覧
- + ITトピックス(12)
- + Agave(25)
- + Salesforce(100)
- + Anaplan(2)
- + 社員紹介(51)
- + サークレイスについて(32)